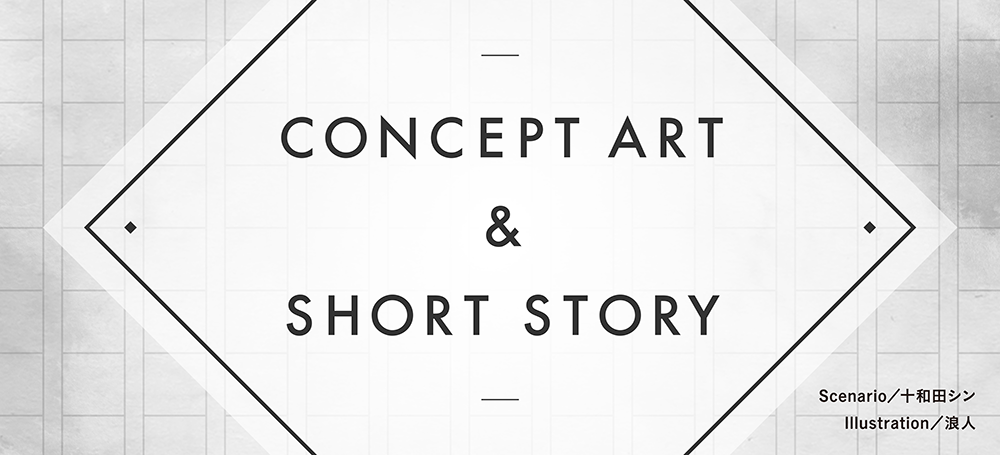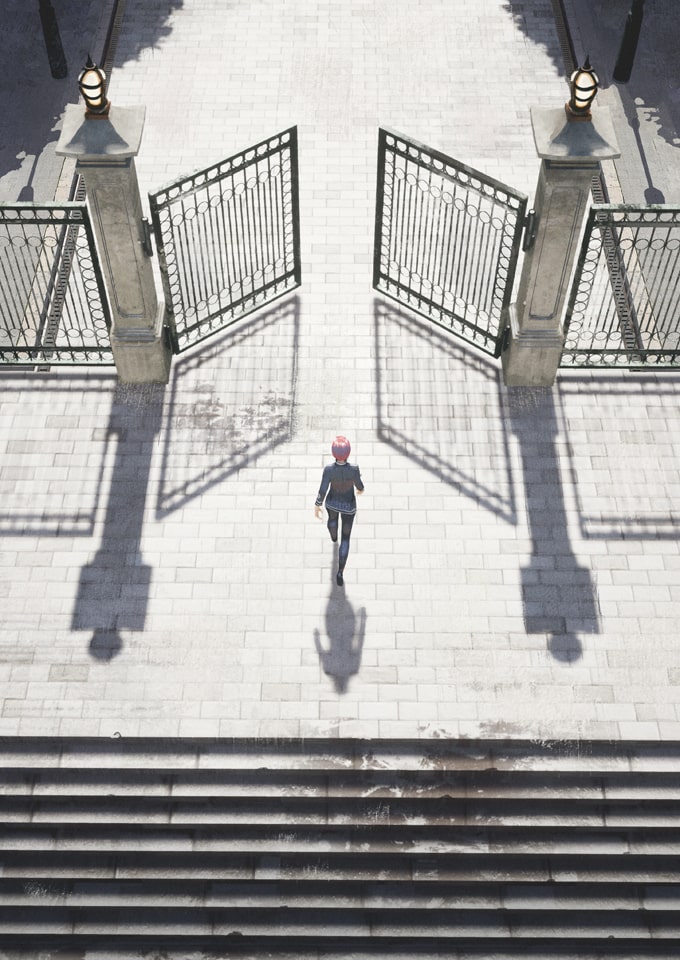「……お疲れさまですっ!」
焦りが滲んだ声が稽古場に響いたのは、フミが稽古場を去って程なくした頃だった。
希佐はダンスを止めて、扉の方へ顔を向ける。
「創ちゃん、お疲れさま」
世長創司郎。希佐たちと同じクォーツ1年の同期である彼は、希佐の幼なじみでもある。
中学に上がる前に彼が引っ越したため、再会はここ、ユニヴェールだった。
昔に比べたら高くなった視線も、低く落ち着いた声も、昔から変わらない優しさのおかげで既になじんでいる。
「お疲れ、世長! そんなに慌ててどうしたよ」
希佐の隣に並ぶスズが声をかけると、世長の眉尻が下がった。
「朝一で自主練するつもりだったんだけど、寝坊しちゃって……」
「また遅くまで本読んでたのか?」
世長の部屋には本棚いっぱいに書籍が並んでいる。読み込むうちに寝る時間を誤り、朝、眠そうにしていることが何度もあった。
しかし今日の理由は違うようだ。
「来週提出の課題が終わってなくてさ。ほら、箍子先生の……」
深いしわのひとつひとつに賢知が滲む箍子数弥は、舞台の歴史や脚本の読み方、他にも、舞台にまつわる様々な事柄を教える座学の講師だ。
「ああ、脚本読んで気になったところ調べろってやつか」
「うん、玉阪座の舞台脚本」
箍子はユニヴェールの母体、男性歌劇の最高峰『玉阪座』の演出も手がけている。その流れで、玉阪座にまつわるものを教材代わりに使うことが時折あった。
「歴史物で、明治の話なんだよね、あれ」
世長の言葉に、スズが 「江戸だと思ってた」 と慌てる。
「世長スゲー真面目に調べてそう。オレ、こういうのニガテだからさっさと出しちまったよ」
「えっ、そうなんだ! 何について調べたの?」
「主人公の奉公先の仕事」
希佐が 「呉服屋だったよね?」 と確認するように聞く。
「そうそう、呉服屋。時代劇でよく見かけるけど、実際どんな仕事してんのかイマイチよくわかんなくてさ。そんな状態で芝居やっても、上手く動けないだろ? だから……」
スズが世長の背後に立つ。
「はい、新しいお着物ですね!」
「えっ」
驚いて振り返る世長のことは気にもせずに、スズが世長の後ろ首に手をそえる。
「では、寸法を測りましょう、身丈はここから……」
スズはその場にしゃがんで、今度は世長のかかとを押さえた。
「……ここまで」
その動きは、それこそ時代劇で、反物を手に寸法を測る呉服屋のようだ。
「スズくん、すごい。動きまで入ってるんだ」
驚く世長に、スズが 「見たからな!」 と胸を張って応える。
「見た? 何を?」
「街の……中小路にある呉服屋で、直接見てきた」
希佐と世長が 「えっ!」 と声をあげる。
「いやだって、本見ても、ネットで検索しても、いまいちピンとこなかったからさ~!」
実際に働いているところを見せてもらったそうだ。
玉阪という街全体がユニヴェールに協力的なのはもちろん、社交的なスズならではの方法だろう。
世長が改めて 「すごいなぁ……」 とため息をつくように言う。
「希佐ちゃんはもう終わった?」
「進めてはいるけど、まだ終わってないよ。脚本に出てくる知らない言葉を調べていたんだけど、ひとつだけ手持ちの資料じゃわからない言葉があって。今日、図書室で調べるつもり」
「あっ、そうなんだ、僕もなんだよ。朝稽古をすませたら、図書室に行こうと思ってて……」
それなのに寝坊をしてしまい、予定がくるったのだろう。世長が肩を落とす。
「今から稽古して、図書室行けばいいだけだって。そんな気にすんなよ」
自己嫌悪に陥る世長をスズが励ます。
「そ、そうだね! こうやって落ち込んでいる時間がもったいないし、2人の稽古も中断させちゃって……。……」
「おいおい、またきた、またそれ! ほら、稽古しよーぜ!」
スズが引っ張るようにして、今度は3人での稽古が始まった。
静かに稽古場を照らしていた太陽は東の空からてっぺんへと移動していく。
「腹減った!」
そして正午を区切りに3人で昼食を食べたあと、歌の稽古をするというスズと別れ、希佐は世長と2人、図書室に来た。
ユニヴェール歌劇学校の図書室は、広大だ。背丈の高い本棚が隊列を組むようにずらりと並び、一般書籍から舞台に関わるものまで、一生をかけても読み尽くせないほどの本が所蔵されている。
「……すごいね創ちゃん。レポート用紙、何枚書いたの?」
学習スペースに横並びで腰掛け、世長がレポート用紙を取り出したところで希佐がその枚数に驚いた。
自主性が求められるユニヴェールらしく、各自それぞれ勉学が身につく選択をと、枚数に規定はなかったのだが、世長のそれは明らかに多い。
「あ、違うんだよ。何をどこまで調べたらいいのかわからなくて、気になったことをまとまりなく書き出しているうちにこうなっちゃったんだ……」
想像力が豊かな世長にとってユニヴェールの自主性は、どこまでも広く続く高原の中、数百数千にも及ぶ羊の群れの面倒をたった1人で見るようなものかもしれない。
「そのせいで寝るタイミングも逃しちゃって……。僕、ホントこういうこと多いや。スズくんみたいに最初から焦点を絞ってやれば良かった」
世長が俯くようにレポート用紙を見つめる。
「希佐ちゃんは朝からスズくんと稽古してたの?」
「うん」
「そっか。2人のダンス、昨日よりずっと、それこそ見違えるように良くなってたから驚いたよ」
「あっ、それは、フミさんに稽古をつけてもらえたからじゃないかな」
「フミさん?」
希佐はフミとの朝稽古を思い出しながら言う。
「朝一で稽古場に行ったらフミさんがいて、ダンスのチェックをしてくれたんだ」
それがしっかり形になっているようだ。
「そうだったんだ……。やっぱり早起きすれば良かったな。フミさんには自分からうまく話しかけられないから」
世長が残念そうに息をつく。
「あ、ごめん、課題があるのに脱線ばかりしちゃって」
話しを切り替えるように、世長が課題の脚本を手に取る。
「そういえば希佐ちゃんのわからない言葉って?」
希佐は脚本を開くと 「ここ」 と指さした。
そこには『誘宵』と書かれている。
「初めて見る言葉で、意味も読み方もわからなかったんだ。創ちゃん、わかる?」
「これ、僕もわからなかったんだ。セリフは……」
男が『誘宵に外をほっつき歩いてどうした』と尋ねるようだ。
それに対して女が『なんでもないわ』と答える。
「うーん、セリフから上手く読みとれないな……。ネットで検索しても、出てこなかったんだよ、この言葉。『宵』が入っているから日暮れ後の夜だとは思うんだけど……でも誘うって。誘う宵……」
世長はヒントを探すようにレポート用紙をめくる。
「……この舞台、初演は明治で、玉阪座の十二代目の玉阪比女彦が演じた舞台らしいけど……」
――玉阪比女彦。
玉阪座の起源は、江戸の中期、全国各地を回っていた旅一座の座長、比女彦にある。
才気溢れる絶世の美少年だった比女彦は、当時、この近辺を治めていた領主にいたく気に入られ、『玉阪』という名と、土地を賜り、舞台小屋――玉阪座を開いた。それが始まりだ。
名は代々受け継がれ、今ではユニヴェール歌劇学校の校長である中座秋吏が十八代目・玉阪比女彦を襲名している。
「人気の舞台だったのかな?」
「それが、早世した十二代目と共に上演されなくなったらしいよ。近年になって復活させたとか。箍子先生も関わっていたみたいだね」
そういう経緯もあって、教材として使っているのだろう。
「この言葉、今は廃れた当時の言葉だったりするのかなぁ」
首をかしげる世長の言葉を聞きながら、希佐は『誘宵』という言葉を見つめる。
そこに、影が差した。
「これは『いざよい』ですなぁ」
「……ッ!?!?」
耳元すぐ側で突如響いた声に希佐は身をすくませる。
見れば希佐と世長の背後から、ぐっと身を乗り出すようにして、クォーツの組長、根地黒門が脚本をのぞき込んでいた。
「ね、根地先輩……! お疲れさまです」
希佐が慌てて挨拶する。
世長も 「お、お疲れさまです」 と続いたが、声はうわずり手は心臓を押さえていた。
「はい、お疲れさまん。休日なのに図書室でお勉強とは熱心だねぇ」
根地が眼鏡を持ち上げにんまりと笑う。
「箍子先生の課題なんです。脚本を調べてくるようにと」
「どうりで渋い。古い玉阪歌劇だね」
根地が希佐の脚本を勝手に取り上げパラパラとめくる。眼鏡の奥の瞳が忙しなく、楽しそうに文字を追う。
「箍子先生は相変わらず趣味がよろしい。『誘宵』なんて言葉が出てくる脚本を課題に出すなんて」
「調べても出てこなかったんです。昔の言葉なんですか?」
「昔の言葉でもあるし、玉阪独自のものでもある」
「『玉阪座』独自の、ですか?」
希佐の言葉に、根地が 「いーや」 と首を横に振った。
「ここで言う『玉阪』とは、『玉阪市』のことよ」
根地は『誘宵』と書かれたページを開き直して、机の上に置いた。
「この言葉は、玉阪市独自の古い言い回しなのさ。でも、聞いたことない? 『いざよい』」
それに、世長が 「あっ」 と声をあげる。
「もしかして……『十六夜』、ですか? 月の名前……新月から数えて、16日目の月」
世長が希佐に教えるように、『十六夜』とレポート用紙に書く。
「さすが、世長くん、月通だね!」
正解だったらしく、根地が世長に向かって拍手した。静かな図書館にやたらと響き渡る盛大な拍手だ。希佐と世長が 「ね、根地先輩!」 と慌てる。そんな2人に根地は逆に 「落ち着きたまえ、お静かに!」 と言って、これまた響く咳払いをひとつした。
「月の満ち欠けには、日本固有の名前が様々にある。十六夜もそのひとつ。先ほど世長くんが言ったとおり、新月から数えて、16日目の月のことだ。月ってヤツは大体、15日目が満月だから、十六夜はその翌日、やや欠けた月を指すことが多いね」
まるで講師のように、根地が朗々と語る。舞台で講師役の人間が専門分野について語っているシーンのようにも見えた。
「この十六夜を、玉阪の人たちは誘う宵と書いて『誘宵』と呼ぶんだ。どうしてかわかるかい」
根地が内ポケットからペンを取り出し、世長をビシリと指す。
「えっ」
「そう! 玉阪では昔から十六夜の晩に、ふらりと姿を消す人が多かったんだ! ……なにかに誘われるようにね」
「こ、答えていませんが……!?」
「そうなんだよ、思い悩む人ほど誘われやすかった……」
世長の戸惑いなど歯牙にもかけず、話は進む。
「だからほらごらん、この『誘宵』が入ったセリフ」
根地が『誘宵』と記された箇所をペンで指す。
「レッツ立花くん!」
「えっ! ……男が『誘宵に外をほっつき歩いてどうした』、です」
気持ちを切り替え、希佐がセリフを読みあげると、世長が 「あっ」 と声をあげた。
「じゃあ、これってもしかして、女性が思い悩んでどこかに消えてしまうんじゃないかと男が心配するセリフなんですか?」
「はい立花くん、ここで返し!」
「女性が『なんでもないわ』です」
「どう思う、世長くん?」
根地が再び世長に問う。
「女性が、悩みなんてない、って返しているんでしょうか。でも……真意をつかれて誤魔化そうとしているだけなのかも……?」
しかし世長は 「ちょっと待って下さい」 と首をひねった。
「男性が軽口を叩いているだけの可能性もあるのかな。冗談っぽく『なんだい、消えちまうつもりなのかい?』って。女性はそれをあしらうように……あー、でもな」
世長の頭の中で様々な可能性が溢れ出しているようだ。
「根地先輩、正解はなんなんですか?」
白旗を上げるように世長が回答を求める。
「世長くん、それはね……」
根地の表情が、スッと真面目になった。真剣な眼差しに、希佐と世長の背筋も伸びる。
「……知らぬ!!」
しかし、答えは予想外。
戸惑う2人に根地がケラケラと笑う。
「正解のない世界で、答えを探し求めるのが面白いんじゃないか~」
その言葉は、不思議と澄んでいた。だから希佐も世長も、何も言えなくなる。
「さてと! シメのキリがヤバシ僕はそろそろ作業部屋に戻ろうかね。このままじゃ僕も誘宵に消えてしまうかも……なんてね、ふはは!」
根地はペンを内ポケットにしまい、ひらりと手を振ると、颯爽と去って行った。
図書室に静寂が戻る。不思議とそれが寂しい。
「脚本……改めて読み直そうかな」
世長が脚本を手にとりぽつりと呟く。
「そうすればこのセリフの真意にもっと近づけるかもしれない……」
もっとわからなくなる可能性もありそうだけどね、と世長が苦笑する。
「それにしても根地先輩ってすごいな。奔放で捉えどころのない人だけど、舞台への情熱は真っ直ぐというか……。……真っ直ぐ……真っ直ぐ、かな?」
表現がしっくりこなかったようだ。世長は少し考え込んでから、良い答えが見つかったのか、顔を上げる。
「求道者、みたいだよね」
「求道者?」
「舞台のこと、常に探し求めてるから。どうしてそこまで、どうしてそんなことまで、ってこと、多いでしょ?」
世長がもういない根地を振り返る。
「根地先輩の求める道の先に、一体何があるんだろうね」